
どうも、そいる塾長です。
今回は私自信がやってしまったセンター試験での致命的な”大失敗”のお話…。
それは国語の第1問、評論文最終問題(6)でおきました。
問題文の「不適切なものを2つ選べ」を読み落とすという致命的な”ミス”。
当時ここの問題は6つの選択肢の中から2つ選ぶ形式だったのですが、そこで問題文をちゃんと読んでいなかった。
「不適切なものを2つ選べ」と太字で書いてあるのにもかかわらず。
最後の問題は本文全体の論旨を尋ねる問題。過去問と同じ形式。だからこそ正答を2つ選べば良いとそんなふうに思い込んでいたわけです。
この”ミス”のパターンは初めてじゃなかった。実は過去問でも経験していたのです。なのに防ぎきれなかった。
これがこんなブログを書くことになるきっかけとなるわけです。
最初に受けたセンター試験では点数を伸ばすことに必死で、本番を意識した練習が不十分だったのかもしれません。
本番思いがけない”ミス”をしたり、メンタルコントロールができなくなったりする可能性。そんなのが全く予想できていなかった。
そしてこのことが原因でここからさらに傷口を広げることになります。
この問題を落とすだけならよかったんです。たった-12点。傾斜配点にすれば3点にすぎない。いくらでも2次試験で挽回できた。だから割り切ればよかったのです。
しかし国語が(自称)得意だった私はそこでそう考えることが出来なかった。
その問題でいつも以上に時間を使ってしまったのです。
「不適切なものを…」という問題文を読み落としたせいで、どうしても解答が選びきれず(正解と思われる選択肢が4つから絞りきれなかったわけです。当たり前です。その選択肢は本文にがっちしているので・・・。)、そのためムキになって何度も本文を読み直したりしながら時間をかけて考えてしまったんです。
気づいたときには手遅れで、第1問終了時に大幅に時間超過。古文漢文に時間が残せなかったのと、その”失敗”にメンタルがやられてしまった結果、史上最低点を「本番」で叩き出してしまいました。
-12点で済むはずのところを、最終的に過去問演習のアベレージから-70点という悲惨な点数でフィニッシュすることになってしまいましたとさ…。
そしてこのわかりやすい”失敗”は翌日の理系科目を受験する際のメンタルにも大きく影響しましたとさ…。
・・・

(お約束のやつ。はい、みなさんご一緒に!ぶるぶるぶる~♪)
こわくなかったですか?(笑)
いや~私は怖い。思い出しただけで震えます。今でも受験シーズンには生徒ではなく自分がテストの問題を解いていてパニックに陥る夢を見るくらいです。
やっぱり夢の中でもパニクっている問題は国語。
得意なのにできない!どうしよう!時間がない!どうしよう!ガバッ!
こんな感じで目が覚めます(笑)
もはやトラウマ。可愛い生徒たちの心にこんな傷を負わせるわけにはいかんとですよ!
ここでの私の問題点は3つ
- 問題文を読み直すという当たり前の作業ができなかったこと。
- そんな問題さっさと飛ばしてダメージを最小限にしようと考えなかったこと。
- そのパターンを事前に想定していなかったこと。
本当のことを言うとこれが原因で浪人したわけではなく単に2次試験に届く力がなかっただけなのですが、やはり浪人時代怖かったのはセンター。
実力が出しきれなかったセンターと、実力を出し切っても届かなかった2次試験。そんな感じでしょうか。
本来なら上にあげた3つは、いずれも過去問演習をする上で想定できたはずのことです。
1、2は当然のことなのですが、なかでも浪人中、最も意識したのは第3の問題点。
なぜ過去問演習ですでにそのパターンを経験していたにもかかわらず私は対策が打てなかったのか。
大切なのはあらゆる場面を想定して演習しておくこと。前回も言いましたが、当然それは学力面での対策とは別のもの。しかしそういうところにまで対処できるように準備しておくということ。(もちろん全てはカバーできないのですが)
それこそが本当の意味での「本番を意識して演習する」ということだと思うのです。
迎えた翌年…、この失敗を踏まえ対策に対策を重ねて迎えたセンター試験本番の国語の最中にあの”想定外”のトラブルですよ(笑)
(トラブルの詳細はこちらからどうぞ↓)
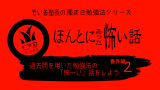
しかしここで私はこの”事前準備”のおかげで踏ん張れたわけです。
流石に動揺したのか、時間配分に少し狂いが生じてしまい、結局最後、漢文に残されたのはたった10分。
確かに10分はきつい。
ただこの時の私は少し焦りながらもあまり心配はしていませんでした。いや、心配していないと自分に言い聞かせていました。
何度も何度も過去問を解く中で、漢文は10分以内に解く練習をしていたからです。
だからからか、大きく深呼吸してから10分で見事全問解ききりました。もちろん満点。ドヤ!
時間が厳しくなることをしっかり想定して練習していたからこその勝利でした。
そして何よりここで満点をとるよりも確実に一点でも点数を積み上げることを冷静に選択できた。これこそがパニックに陥らず、いつもどおりに一問一問、問題をこなせた理由だろうと思います。
事前に想定していたからこそ、落ち着くことが出来たのです。もちろん残り時間を見た時にはお腹の奥が気持ち悪くなるような感じはありました。
ざわざわ・・・と。
でもその「ざわざわ感」すらも経験したことがある人なら対処可能かもしれないということです。
そんなものをかき消すほどの強靭なメンタルを作っておくとでも言いましょうか。
もちろん一流アスリートみたいなレベルのものは不可能かもしれません。それでも自信は持って臨みたい。
セルフトーク
そこからは、完全にゾーンに入った感じです。あそこまで集中できたことは練習でもなかったかもしれません。
でもやはりこれは、何度も何度も通し稽古方式で本番を意識した結果だと思います。これが浪人してから変わったこと。
ちなみにこういうのをセルフトークと言うらしいです。
↓のイチローさんの自分で実況中継してメンタルを整えたエピソードは興味深いです。
ぜひ読んでみてください。
私は勉強するとき自分と会話しながら解くんですよ。自分の部屋だと完全に声出して喋ります。
あ、気持ち悪いですか?(笑)
でも、これが意外と良いのです。
セルフティーチングといいますか、自分で自分に教える感じで普段から一人で誰かと会話しているように勉強してきたのもあってなんか癖なんですよね。その影響からか、ピンチのときもこの自分との対話で結構客観的に見ることができます。
今でも考え事してるときはこれなんで、時々突然独り言のように声に出てしまうことがあって。
受験シーズンとか、新しい企画を考えているときのように頭がぐるぐるまわっているときなんかは道を歩いていると突然独り言を言い出すもんで自分でもびっくりするんですよね。
家族にはがっつり気持ち悪がられます(笑)
時間配分をマネジメントする
私は基本的に解くのが遅いので、センター試験の英語や国語は時間がカツカツです。
当然これが現役当初の”大失敗”につながったわけです。
時間配分は過去問演習時の最大の課題。
だから過去問演習のはじめの方は一問一問ストップウォッチのラップタイムを使って解く時間を計測していました。
計測結果から時間と正答率の相関関係を分析し(あ、分析と言ってもなんとなく雰囲気で決めてただけ)、何分以上かけてわからなかったら飛ばすという自分ルールを模試の時からしっかり事前に決めていました。
毎回同じペースで解き、解くリズムを体におぼえさせる。時計を見なくても経過時間がわかるくらいに。
これは私がボクシングをかじってたからかもしれません。ボクシングやっていた時、ジムでは3分おきにかならずゴングが鳴るように設定してあったので自然と3分という時間を体で覚えました。
問題を解くリズムを体が覚えているので、試験中でも時計を見る前にだいたい経過時間がわかるんです。そのリズムがずれていたら緊張しているということですね。
もしも、問題形式が変わっていたりすると、必ずその問題は飛ばして最後に解くということも決めていました。
また見直しという生産性のない作業をするくらいなら見直しをしなくてもいいように解くという変なポリシーを持っています。
ミスする前提がおかしいんです。それに全問題見直しなんか出来るはずない。
だからこのブログも誤字脱字だらけなんだと言われそうですし、仕事でもしょっちゅうなので保護者の皆様には申し訳ないですが。
こうみえて意外と入試本番ではミスしなかったんですよ、わたし。でもこれは現役時の”大失敗”から学んだのが大きかったなと。
ただどんなに練習しても入試問題は毎回異なるので、どうしても時間配分に誤差はでる。
そのため5分~10分の余裕は作ります。そのため練習ではいつも最低5分短く解き切るようにしました。
本番は緊張から気付かないうちに解くペースが速くなり、雑な解き方をしてしまう人もいます。
だからあせって10分残すようなことはせず、ペースが速すぎれば深呼吸して一旦ペースを落とします。
見直しして解き直すと逆に間違えることがあります。国語や英語長文では最初に読んだときのほうが頭に入っている情報量が多いので実は正解に近いなんてことも。
見直しは難しくて時間がかかると考え、難しくて飛ばした問題とかマークミスがないかの確認とかに限定したほうがいいかと思います。
失敗しないメンタルトレーニング
こういったメンタルだから本番失敗するんです。やるべき準備を怠っている。こうして起きたミスは偶然ではなく必然なんです。ならばミスとよんで処理しちゃいけませんよね。
そして、そういう考え方ができないからいつまでたってもメンタルが強化されないのです。
そんな人は入試を運良く乗り越えても、社会にでて入試よりも、もっともっと重要な場面で緊張してしまって実力が発揮されないのでは大変です。
せっかくの受験勉強。しょーもない受験テクニックを身につけるよりも、こういった役立つ能力を身につけて「出来る人」になりましょう。
ということで最近話題のメンタルトレーニング。
例えば先程ご紹介したイチロー選手。イチロー選手のルーティンは有名ですよね。これはいかに練習と本番を近づけるかを考えてのもの。
体操の内村航平選手は練習で120%、本番で100%の力を出すとも言ってましたね。
受験ごときにそんなもの必要ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一回限りの勝負をする上では同じ。
本番に力を発揮できないようでは今までの努力は何だったのかという話です。
プラシーボ効果
例えば過去問を解く時間帯。夜型の人が入試にあわせて朝方にするのは当然です。
それだけではなく本番と同じ時間に、過去問を解いてみましょう。これで朝だからどうのこうの言い訳しなくて済みます。
朝ごはんは本番の日だけ食べるとか論外。食べるなら食べる。食べないなら食べない。
間違っても入試当日にカツとか食べないwそんなご飯だしてくるバカ親は事前に自らしっかり教育しておく(笑)
朝お腹が痛くならないようにトイレに行く練習。それでも心配なら常に薬を持ち歩いておいて、飲んだら痛みが収まるということを確認しておく。
それに科学的根拠があるかどうかとかどうでもいいのです。大切なのはいつもどおりできると自分に思い込ませること。
言うならプラシーボ効果かな。要は科学的根拠はないかもしれない。
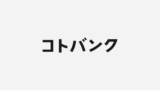
心理学の知識はありませんので科学的根拠を伴ったメンタルトレーニングのお話は出来ませんが、こうやって本番を意識して毎日練習することで、本番のイレギュラーが日常の当たり前のこととなり、本番緊張を生み出す因子を減らすことが出来る。私はそう考えています。
あと最後にこれ。
毎晩寝る前に明日が入試と思って緊張してみる。
で、眠れなかった日の朝に過去問を解いてみれば別に眠れなくてもそんなにパフォーマンスは変わらないということがわかる。
駄目なのはこういうことを直前まで考えず、入試前日に急に心配しだすこと。夏休みの宿題と一緒です。まだいいだろう、まだいいだろうが生み出す”失敗”。
さすがにインフルエンザに事前にかかっておけとは言いません。もちろん予防注射は打っておくw
これをせずに当日インフルエンザで熱を出すとか無能の極致。
試験当日39度の熱を出したお前が言うなと言われそうですが、私は結局浪人して迎えたセンターは過去最高点。エッヘン
そんなもんでは鍛え上げられた私のメンタルは崩れないのである。
あっはっはっは!
あ…、でも高校入試のときも高熱出したんですよ。でもそのときは滑り止めの高校の入試だったので気合も入らず数学と英語の半分解いてギブアップしました(笑)
そうです。
受験において大切なのは肉体よりもメンタル。
自分に言い聞かせることで自分ではコントロールできない体調を超越するんですよ(笑)
オリンピックで羽根田選手も体調不良を跳ね返してメダリストになりましたね。
もちろん風邪を引かないというのも能力の一つ。体調は万全なほうが良いに決まっています。
体調管理を1年間しっかり意識して行っている人と、入試直前だけマスクを付ける人では根本的に自己管理能力が違うということです。
例えば元旦の初詣。なにも1日の大混雑の中行かなくても・・・。
そんなことしてるから風邪をうつされるんですよ。初詣は空いた時期にゆっくりいきましょう。
そして手洗い、うがいは毎日しっかりと。
こういうのを毎日当たり前にしっかりやっていることが大切なんです。
「あのときちゃんとやっていれば…」これだけはやめましょう。一生消せない心の傷になりますよ(笑)
心配性万歳
もうお気づきかと思いますが私は心配性。しかも極度の(笑)
にもかかわらずズボラというAB型特有の2重人格的な性格です。(血液型占いとか信じませんが)
しかしここまでズボラでもなんとか受験を乗り越えられたのはもう一つの心配性な人格のおかげ。
心配症な人は入試の半年前くらいから緊張するもんです。プレッシャーに押しつぶされそうになると思います。

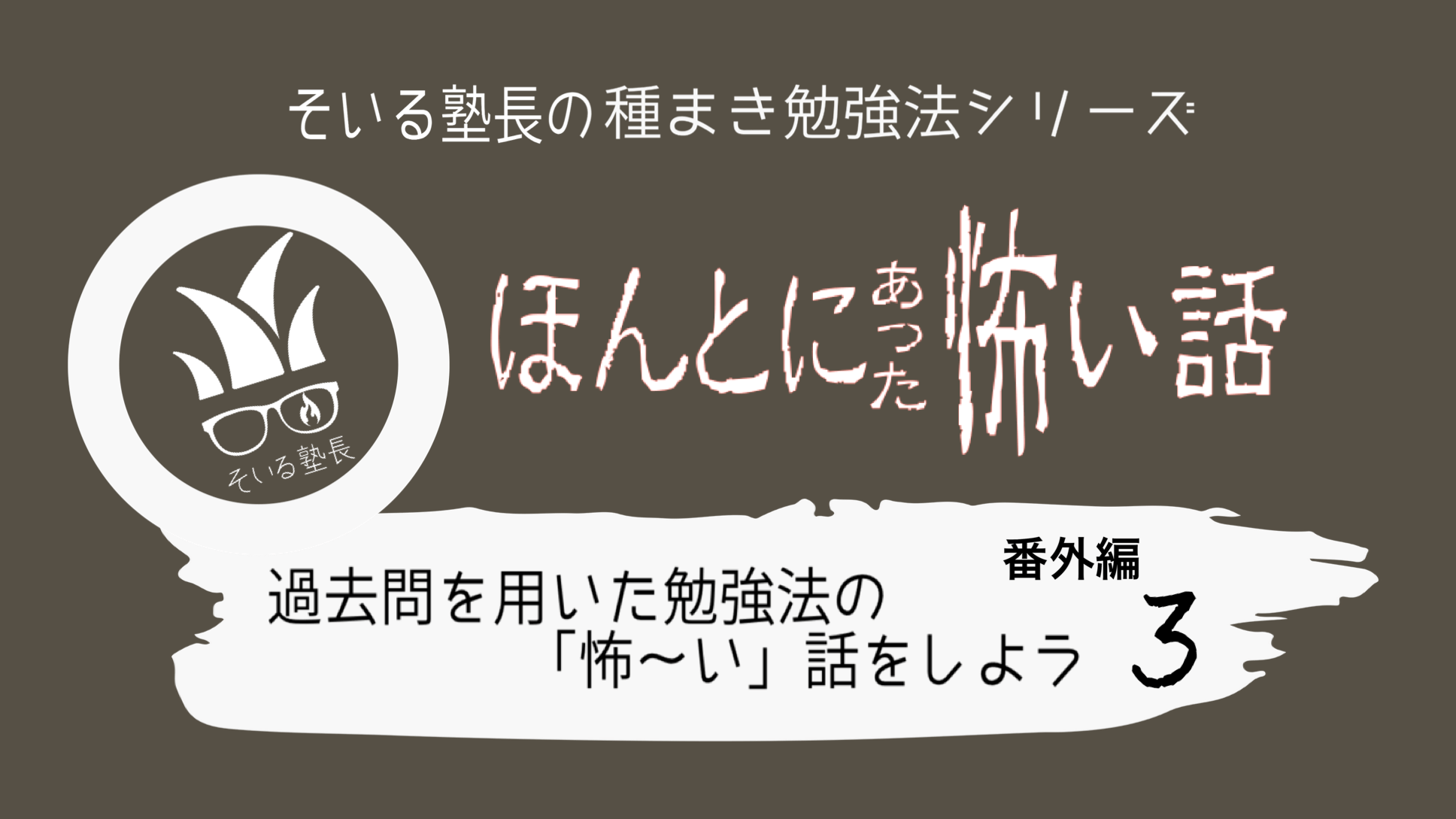
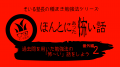
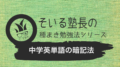
コメント